WCSC35(第35回世界コンピュータ将棋選手権)でやねうら王チームが使用した定跡をMIT Licenseで無償で公開することにしました。
事の経緯は、5年ほど前に、このブログで詰将棋局面を500万問公開したことに始まります。
やねうら王公式からクリスマスプレゼントに詰将棋500万問を謹呈
https://yaneuraou.yaneu.com/2020/12/25/christmas-present/
これは、Twitter(当時)で私がクリスマスプレゼントに欲しいものを(ジョークとして)アンケートで聞いたのが発端です。

詰将棋問題100万問という前代未聞のスケール感(ある種のボケ)に、「そんなに解けねぇよ!」というツッコミを頂戴するという、言わばそういう類のユーモアではあったのですが、しかしアンケートの集計が終わった時に、「本当に詰将棋問題100万問を公開したら面白いんじゃないか?」と考えなおし、本当に公開してしまいました。
この時、勢い余って3,5,7,9,11手をそれぞれ100万問ずつ、合計500万問公開しました。
この規模の詰将棋問題セットは、当時としては画期的で、そして、いまだにこの規模の詰将棋問題のデータセットを公開している人は他にいないので、もしかすると5年経ったいまでも画期的なのかも知れないです。
そして、この5年間に様々な人がこのデータセットを活用してくださったようです。
・VTuber/YouTuberが動画の企画として
・自身のトレーニングのために
・教師データとして(詰将棋の正解は100%正しい神の一手なので教師データとしての価値がある)
・将棋AIの研究用途で
また、最近では、以下のアプリで使わせていただきましたとこの会社の担当の方から連絡をいただきました。
本件、金銭の授受は発生していませんが、こうやって公開したデータセットを色んな方に使っていただけるのは嬉しい限りです。
https://crossfd.co.jp/products/app02.html
これからも、将棋界隈の進歩につながるデータセットを公開していきたいと思います!
と決意したところで、同様にいま掘っている定跡も無償で公開すれば、誰かの役に立てるのではないかと思いました。(前置きが長すぎ)
そこで、WCSC35(第35回世界コンピュータ将棋選手権)でやねうら王チームが使用した定跡をMITライセンスで公開することにしました。
本大会では、やねうら王は、2時間ごとぐらいに定跡を差し替えていたのですが、この定跡は、決勝日の一番最後に使用したものです。
新ペタショック定跡 233万局面
https://github.com/yaneurao/YaneuraOu/releases/tag/new_petabook233
// 「Assets」をクリックして new_petabook_20250505c.7z をダウンロードしてください。
将棋ファンの方や、将棋AIの研究者、開発者の方など、皆様にご活用いただければ幸いです。
また最新の新ペタショック定跡は、やねうら王の支援者向けに配布しています。(6月のNews Letterで2771518局面のものを配布しました。7月には、3371226局面のものを配布する予定です。) 興味のある方は、そちらもご覧いただければと…。
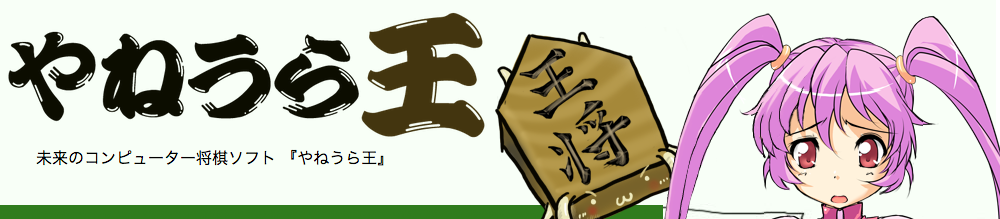
そろそろ、囲碁もやってほしい気がします。
deepLearningで。
なんか、将棋だと、日本だけだから、もったいないなー、といつも思ってます。
麻雀世界戦、アベマでやるみたく、視野は広く。
囲碁AIは、国内にもっと大きな大会があれば挑戦する気にもなるんですけども…。
やねうらお様
いつも楽しく拝見させていただいています。
自身も趣味で棋譜開拓をしているものですが、ご存じ、ないしお考えがありましたら、ご教示下さい。
AI将棋界において、「定跡」と呼べる手順は、どの程度バリデートされているものを示すのでしょうか。AI同士が指しあって出来た局面図の集合体と、勝敗の発生割合がどの程度再現できるものを定跡と呼ぶ、などの決まり(あるいは、こだわり)はございますでしょうか?
もし場違いな書き込みとなりましたら、大変失礼致しました。その際はお捨て置きください。
> 勝敗の発生割合がどの程度再現できるものを定跡と呼ぶ、などの決まり
このへん決まりはないです…が、考えていることをいくつか書いておきます。
たややんさんは、定跡を掘るときに基準ソフト(例えば水匠10、1億ノードの探索)で評価値の絶対値が400を超えたら勝ちとみなして定跡を掘り進めています。
評価値の絶対値が400を超えていれば、入玉が絡まない限りほぼ逆転はしないからです。
それで評価値の絶対値が400以下の局面については、「結論が出せていない局面(掘り足りないから、さらに掘って結論を出すべき)」という扱いではあります。
私も評価値の絶対値が小さいうちは、「結論が出せていない局面」であるという認識です。いわゆる「定跡」にはまだほど遠いという考えです。ただ、そういう局面もすべて含めて、将棋AIで生成したものを(広義の)「定跡」と呼んではいます。
やねうらお様
お忙しいところ、ご返信頂き、誠にありがとうございました。
400点というところも、最新の関数に基づくものだと思いますので、昔の関数では定跡と言われていた部分が、今では定跡から外れる結論に至った、ということもあり得るのだな、と理解致しました。
きっと、定跡ファイルに記述されている内容でも、人間がまだ目にしたことがない手順もたくさんあるのでしょうね。
ファンでしたので、ご返信いただけて嬉しかったです。ありがとうございました。
すいません、ざっと見ただけで勘違いだったら恐縮なのですが、これは先手専用定跡なのでしょうか?後手番局面が見当たらない気がします。
https://github.com/yaneurao/YaneuraOu/releases/tag/new_petabook233
に書いてあるエンジンオプションのうち、FlippedBookをオンにしていないからではないかと…。
爆速の回答ありがとうございました。 実は正規のエンジンではなく、この定跡ファイルをブラウザでみられる自前の将棋盤アプリから拾わせてみたのですが、その際、FlippedBookをONという供述があったので、急遽Javascriptでsfenをフリップする関数が必要になり、AIに聞いたらあっさり回答をくれたのでそのままPLYだけ0にして使っていました。これがバグっていました。(\2P6\などの文字列を逆転させていなかった)。 hitしないわけです。大汗! AIは誰かのコードをwebから拾ってきたのでしょうが改めて他人のコードは鵜呑みにしてはいけないと認識した次第です。 大変失礼いたしました。
ブラウザで見られるんですか!それは素晴らしいです!!
そう言えば、私も盤面をflipさせるコードをChatGPTに書かせてハマったのを思い出しました。
https://yaneuraou.yaneu.com/2023/12/15/chatgpt-wrote-a-program-to-flip-a-shogi-board/