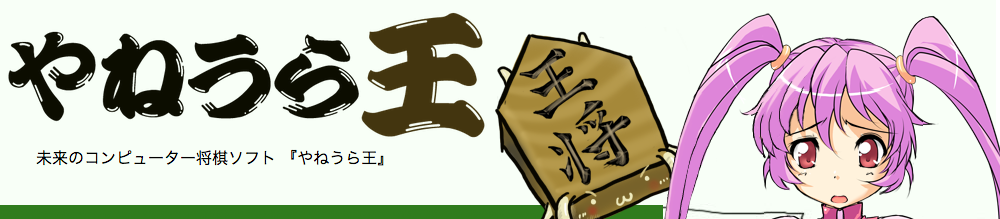将棋AIの強さの計測は、互角に近い局面から対局を開始させる。この選び方が難しい。
ある人は、(自分が使う)定跡の末端の局面からにしたほうが、現実的な強さを反映するという主張する。しかし、それに合わせて探索部の調整を行ってしまうと、定跡が変化した時に弱くなってしまうし、普遍的な強さではないと思う。
またある人は、現代では将棋AIの戦いは角換わりがほとんどなのだから、角換わりの戦型のうち、互角の局面を抽出すべきと主張する。一理あるが、これも、それに合わせて探索部を調整すると角換わりだけが強い将棋AIになってしまう。角道を序盤早々にとめられた途端に勝率が○○%低下する。そんな将棋AIでいいのだろうか?
またある人は、ランダムムーブN手で開始したあとの局面から将棋AIで互角に近い評価値の局面を使うべきだと主張する。これも一理あるが、実戦とかけはなれた局面(例えば98香~99角の穴角)も混じってしまう。そんな局面での勝率にどれほどの意味があるのだろうか。
このように、どんな戦型から互角局面を選ぶかという問題がある。しかしそれとは別に、それをどうやって互角だと判定するのかという問題もある。
将棋AIで実際に思考させて判定すればいいじゃないかと言われるかも知れないが、弱い将棋AIで判定したのではその「互角」の精度が低いのである。そうすると、(いまどきの将棋AIで対局させると)必ず先手が勝ってしまう局面や、必ず後手が勝ってしまう局面、みたいなものが混じってしまう。こういう局面がたくさん含まれていると、(強さに大きな差のある将棋AIであっても)勝率が5割に近づいてしまう。これでは意味のある計測はできない。
実際、やねうら王プロジェクトでは、9年前に互角局面集を公開した。
このときは、当時のソフトで1手depth18(1秒ぐらい?)の思考時間で、評価値の絶対値が100以下である局面を「互角」とみなして使っていた。
今回配布する「やねうら王互角局面集2025」では、水匠10で1スレッド2億ノードで探索させ、評価値の絶対値が50以下である局面を「互角」とみなすことにした。前回の「互角」かどうかを判定した将棋AIは、レートで言うとR3500前後のプレイヤーだと思うが、今回はR4500前後ぐらいのプレイヤーだと言えると思う。つまりR1000も上がっているわけである。精度が雲泥の差だ。
そして、現在生成している新ペタショック定跡(巨大定跡)の局面から抽出した。これにより、実戦に高い確率で出現しうる戦型から選ばれることになる。角換わりは多いだろうけども、角換わりだけでもなく様々な戦型が含まれる。
初期局面から24手目、32手目の局面で、それぞれ30053局面、26273局面ある。MIT Licenseにて配布するので、是非活用していただきたい。
https://github.com/yaneurao/YaneuraOu/releases/tag/BalancedPositions2025