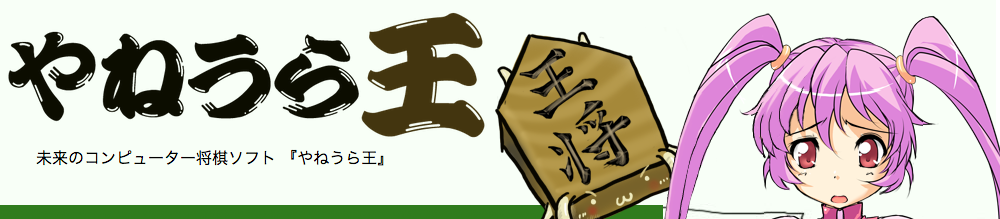コンピュータ囲碁の世界では、長きに亘り良い評価関数を設計できずに苦心していました。評価関数というのは、人間で言うと大局観に当たる部分です。この部分をうまく設計するのが強い囲碁ソフトを作る上で必要不可欠なのですが、それは職人のような作業だと言われていました。
「コンピューター将棋全般」カテゴリーアーカイブ
2倍の思考時間を使うと人間はR200上がるという根拠について
2つ前の記事で、「将棋ソフトでは、2倍の思考時間を使うとR200程度上がります。R200は勝率で言うと約76%。」というのを人間にも当てはめたのですが、それは人間では成り立たないのでは?という意見が散見されるのでこれに対して私の考えを書いておきます。
40コア以上でのLazy SMPの効率改善について
将棋ソフト『PAL』の山口さんからWCSC28のときに、やねうら王およびStockfishのLazy SMPの部分のコードだと、コア数が増えてきた時に同じdepthを探索しているスレッドが増えすぎて良くないのではないかという指摘があった。
藤井聡太さんと最下位のプロとの読みの速度はどれくらい違うのか?
いまや将棋ソフトがトッププロより強いことは周知の事実ですが、プロ集団の棋力の個人差はどれくらいあるのかについて今回は考えていきます。
NNUE型評価関数はAVX-512化で速くなるのですか?
AWSでコンピューター将棋のためにvCPUの多いインスタンスを探すとm5.24xlarge(96 vCPU)やc5.18xlarge(72 vCPU)などが見当たりますが、どのCPUが最強なのでしょうか?
将棋ソフトは不成を生成するとどれくらい弱くなりますか?
歩の不成や香の敵陣2段目での不成、そして大駒の不成は打ち歩詰めが絡まない限り読む必要がない。なので、本来は読みの末端で打ち歩詰めが出現してから、その手前の局面でだけ不成の指し手を生成すればすれば良い。
【ポエム】人間の知性を推定するAIについて
将棋ソフトで、対局後に自分の将棋の棋力を判定して表示してくれるものがある。あれは自分の弱点がわかってなかなか面白いと思うが、プレイヤーの棋力判定というのは、そういう自分が参考になるというだけではなく、オンラインゲームのマッチングにおいても重要である。
【決定版】コンピュータ将棋のHASHの概念について詳しく
いまどきの将棋ソフトを使っていると、「HASH 50%」などと表示されている。これはHASH利用率と呼ばれる。この数字が大きくなってくると探索の効率が悪くなる。要するに潤沢にメモリがある場合に比べると弱くなる。これは、どれくらいの値までであるなら適切なのか?HASH利用率が99%にならない限りHASHには余裕があるものなのか?HASHはどういう仕組みになっているのか?HASH利用率が50%の状況で、ハッシュ衝突はしているのか?など、わりとソフトを長年使っていても知らない人が多いのでここに原理から詳しく説明した決定版的な記事を書く。
AIから人間が学ぶ方法について考えてみた
ゲームAIに関しては、オセロ、チェス、将棋、囲碁とすでにトッププロでも敵わないレベルに到達した。これらのゲームAIから人間が学ぶにはどうすれば良いのかということについて考えてみる。
『将棋神やねうら王』で書き出したKIFファイルが『柿木将棋』で読み込めない件
結論から言うと、『柿木将棋』の棋譜読み込みがUnicodeに対応していないためです。