今年もCODE VSの季節がやってきました。プログラマ日本一決定戦だそうです。
問題についてのヒントになるといけないのであまり詳しいことは書けませんが、今回は同時に多くの自軍のゲームユニットに命令を出して敵軍と戦うタイプの戦略型ゲームとなっています。
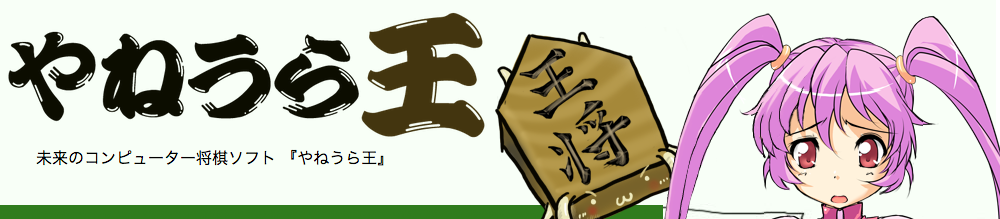 育毛剤最新比較極
ミュゼ 口コミ 特徴 まとめ
育毛剤最新比較極
ミュゼ 口コミ 特徴 まとめ
今年もCODE VSの季節がやってきました。プログラマ日本一決定戦だそうです。
問題についてのヒントになるといけないのであまり詳しいことは書けませんが、今回は同時に多くの自軍のゲームユニットに命令を出して敵軍と戦うタイプの戦略型ゲームとなっています。
今回はmove pickerと言って、指し手を段階的に生成して、生成した指し手のなかから1つ一番よさげな指し手を取り出す部分(いわゆる指し手オーダリング)について見ていきます。
killerが2本あったり、なるべくソートが要らないように工夫してあったり、なかなか興味深いです。
今日はクレクレ乞食をやってみたいという人向けに、私のような有名人(?)がネットでクレクレ乞食をするとどうなるかご紹介しましょう。
https://twitter.com/tb158/status/554942780611371008
羽生先生がTata Steel Chess Tournamentのインタビューに答える形で将棋とチェスの違いを語っています。
Tata Steel Chess 2015 – En passant – Yoshiharu Habu
棋譜からの学習なり何なりで入力棋譜がCSA形式やKIF形式ということはよくあります。しかし、いまや将棋ソフトの思考エンジンはUSIプロトコルでやりとりするのが標準的であり、USIプロトコルでの局面形式(sfen)の入出力部しか書いていない & 書きたくないという開発者の方も多数おられることでしょう。
私の家の先月の電気代の請求が来ました。消費電力から計算してみると定跡生成のために使用したPCの電気代はおおよそ5万円。まだ1ヶ月ほど回さないと思っているところまで生成が終わらないので結局定跡生成には10万円ほどかかる見込みです。
今回はStockfishの指し手生成についてです。チェスと将棋では駒の特性が全く違うので、チェスを将棋に変更する場合、この部分は全面的に書き直しが必要となります。
面白いことにチェスではポーン(pawn = 将棋で言う歩)以外は移動に上下の対称性があるので先後の区別がありません。先手も後手も盤上で同じ動きをするので、将棋のように先手用の指し手生成と後手用の指し手生成とを分ける必要がありません。
続きを読む
今回、電王戦でponanzaと戦う村山慈明(むらやま やすあき)七段の電王戦公式動画が非常に興味深いです。
村山七段「ポナンザとやるっていうのがちょっと誤算なんですね。ポナンザ以外だと結構僕も勝率良かったんですよ。やねうら王とか習甦とかもよくやってたんですけど。(電王戦出場が)決まる前に。やねうら王とか全然…少なくともその入っているパソコンで勝負した感じは全然僕のほうが強かったですね。ポナンザは全然次元が違うんですよ。強さの次元も違う上に感覚の次元が違いすぎて、ついていけないんですよ。」
続きを読む
最強最速アルゴリズマー養成講座 プログラミングコンテストTopCoder攻略ガイドの著者として名高い高橋 直大さんがコンピューター将棋の開発に興味を持っておられるようです。
prediction(棋譜との指し手一致率)が上がっている限り棋力は上がっていくと言う話をpredictionと棋力との関係に書きました。
ボナメソで学習させるとしてもiterationが50を超えた辺りからpredictionの伸びは非常にゆるやかになっていきます。ついでに言うと、条件によっては、このあと学習させればさせるほど弱くなっていきます。
人はこれを過学習と呼ぶかも知れません。
しかし本当にこれは過学習でしょうか?