第29回世界コンピュータ将棋選手権(WCSC29)で、『やねうら王 with お多福ラボ2019』は優勝しました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
手短にいくつか印象に残った試合と簡単な感想を書いておきます。
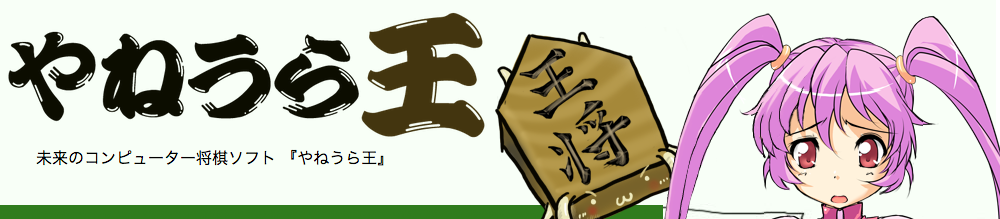 育毛剤最新比較極
ミュゼ 口コミ 特徴 まとめ
育毛剤最新比較極
ミュゼ 口コミ 特徴 まとめ
第29回世界コンピュータ将棋選手権(WCSC29)で、『やねうら王 with お多福ラボ2019』は優勝しました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
手短にいくつか印象に残った試合と簡単な感想を書いておきます。
WCSC29、予選二日目、やねうら王は二位で通過しました。
いくつか書き留めておきたいことがあるので、ざっと書きます。
朝、起きて時計みたらAM 11:55ってなっていて、あー、これはまたやらかしたなーと思ったのですが、心臓がバクバクしながら、もう顔洗って大阪に帰ろうと顔洗ってからよくその時計を見たら、AM 11:88 kHzって書いてあって、どうやらこれはAMラジオの機械だった模様。
ドワンゴさんの『将棋電王トーナメント』がなくなってしまったので、コンピュータ将棋の唯一の大会は、毎年ゴールデンウィーク中に開催される『世界コンピュータ将棋選手権(WCSC)』のみとなってしまいました。今年は、やねうら王も参戦します。
続きを読む
WCSC29(第29回 世界コンピュータ将棋選手権)の出場チームに対する解説をsuimonさんが記事にされています。
2016年に互角局面集というのを本ブログで公開した。従来、強くなったかの計測は将棋所を用いて定跡なしで自己対局させていた。しかしそれだと同じ進行・同じ戦型に偏るため何らかの互角に近い局面を用意する必要があった。
先日100テラショック定跡を公開した。本記事では、その生成手法について詳しく書く。
100テラショック定跡公開しました。