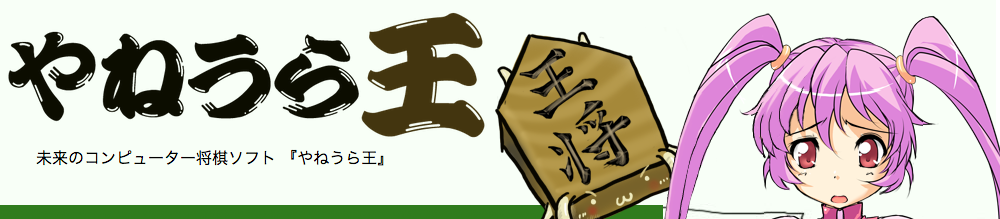2つ前の投稿で羽生先生のインタビュー記事の発言を取り上げたらプチ炎上しました。私は特に炎上を狙ってやっているわけではなく、羽生先生の発言が将棋AI界隈に悪い影響が残り兼ねないので書いたのですが、開発関係者からは一定の同意が得られたものの、将棋ファンからは殺害予告やら、こんなツイートやらが届く始末です。
続きを読む「将棋電王戦」カテゴリーアーカイブ
渡辺明名人と東大教授で日本の脳研究の第一人者である池谷裕二先生との対談記事が間違いだらけである件
ここまでひどい記事は久しぶりだ。
渡辺明名人の疑問「将棋の初手でこれを指したら負けという“必敗”の手はありませんか?」 脳研究者の答えは…
https://number.bunshun.jp/articles/-/846635
多くの将棋ソフトで256手ルールの実装がバグっている件
256手ルールというのは、電王トーナメントなどで採用されていた、256手に達したら引き分けというルールである。強いプレイヤー同士の対局では平均手数が伸びる傾向にあるようで、最近ではコンピュータ将棋の対局でも入玉模様の将棋の割合が増えてきたため、WCSC29では320手、電竜戦では512手に変更されている。以下では規定の手数になれば引き分けとなるルールのことを「256手ルール」と書く。
続きを読むOSSの将棋ソフトは何故一つになれないのか?
やねうら王系の将棋ソフトで採用されているNNUE評価関数がコンピューターチェスの代表格であるStockfishにportingされ、Stockfishのほうで驚異的な強さを発揮し、Stockfishに正式にマージされるのではないかというまでの勢いを見せている。WikipediaにNNUEの項目まで誕生した。
続きを読む1手1秒で強い将棋ソフトは1手10秒でも強いのですか?その2
1手1秒で強い将棋ソフトは1手10秒でも強いのですか?その1
「1手1秒で強い将棋ソフトが1手10秒でも強い」とは限らない。しかし、それはどういう条件の時にそう言えて、どういう条件の時にそう言えないのだろうか?これがわかると短い持ち時間で探索をチューニングすれば長い持ち時間で対局させた時も強いソフトが作れるはずである。
教師データはWCSC28終了まで公開しておきます
Apery(SDT5)の評価関数はどれくらい強いのですか?
本大会で最強の評価関数はAperyのものだと私はくどいほど言い続けたが、それを確認しておく。
何故、SDT5までにやねうら王は強くならなかったのか
今回、やねうら王は公開しているバージョンからほとんど強くすることが出来なかった。(KPP_KKPT型 評価関数でelmo+R170、探索部で+R20程度。elmo+rezero8 = relmo8がelmo+R120程度なので+R70ぐらいしか強くなっていない。) 私の本業のほうが忙しかったこともあるが、それを差し引くとしても、課題に対する取り組み方とか、方針の立て方とか、色々反省すべき点は多い。他の開発者が同じ轍を踏まぬよう、その原因をざっと書いておきたいと思う。
256手ルールが前大会から改変されていた件
今回の電王トーナメントで256手ルールが問題になった。